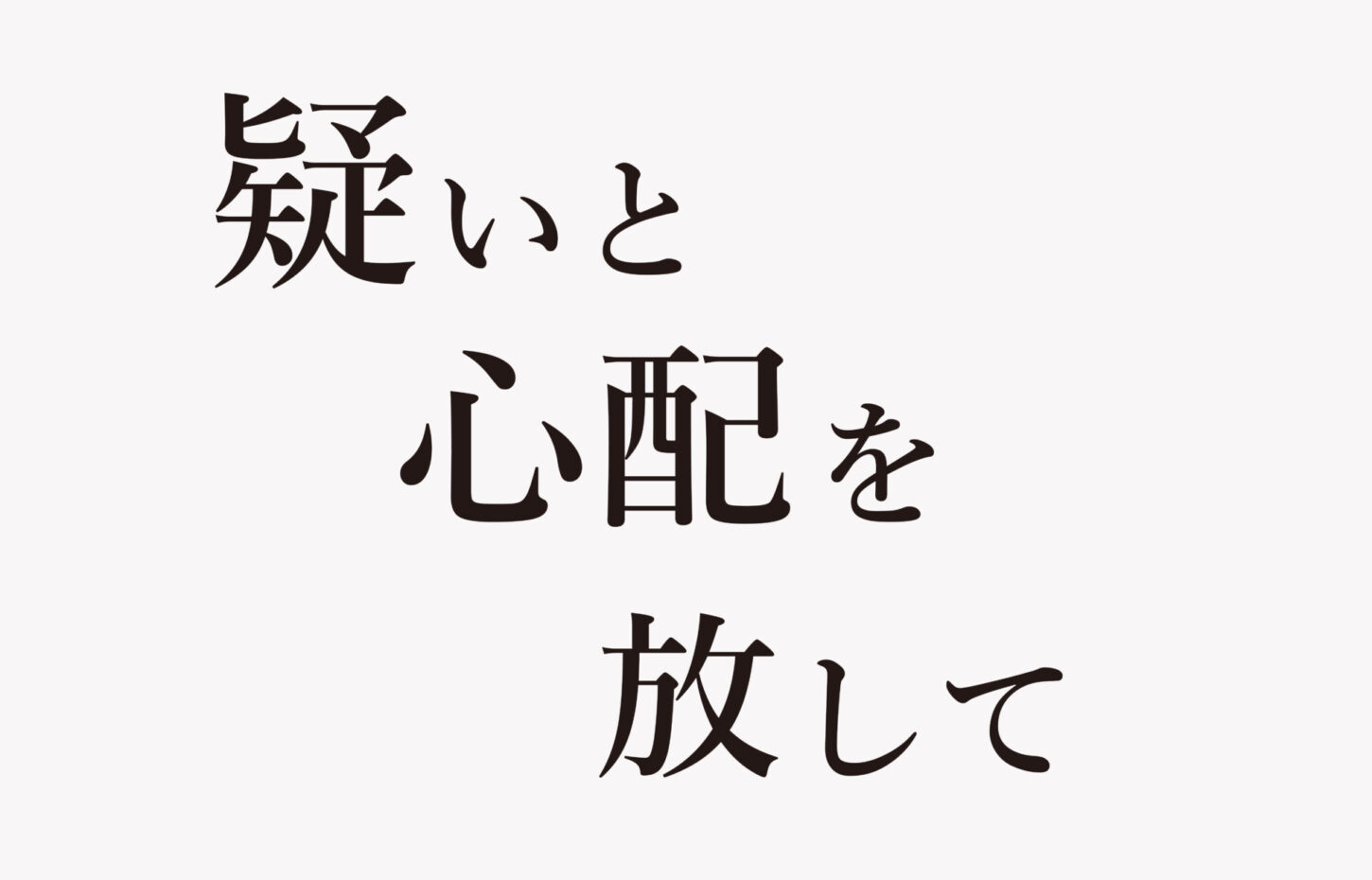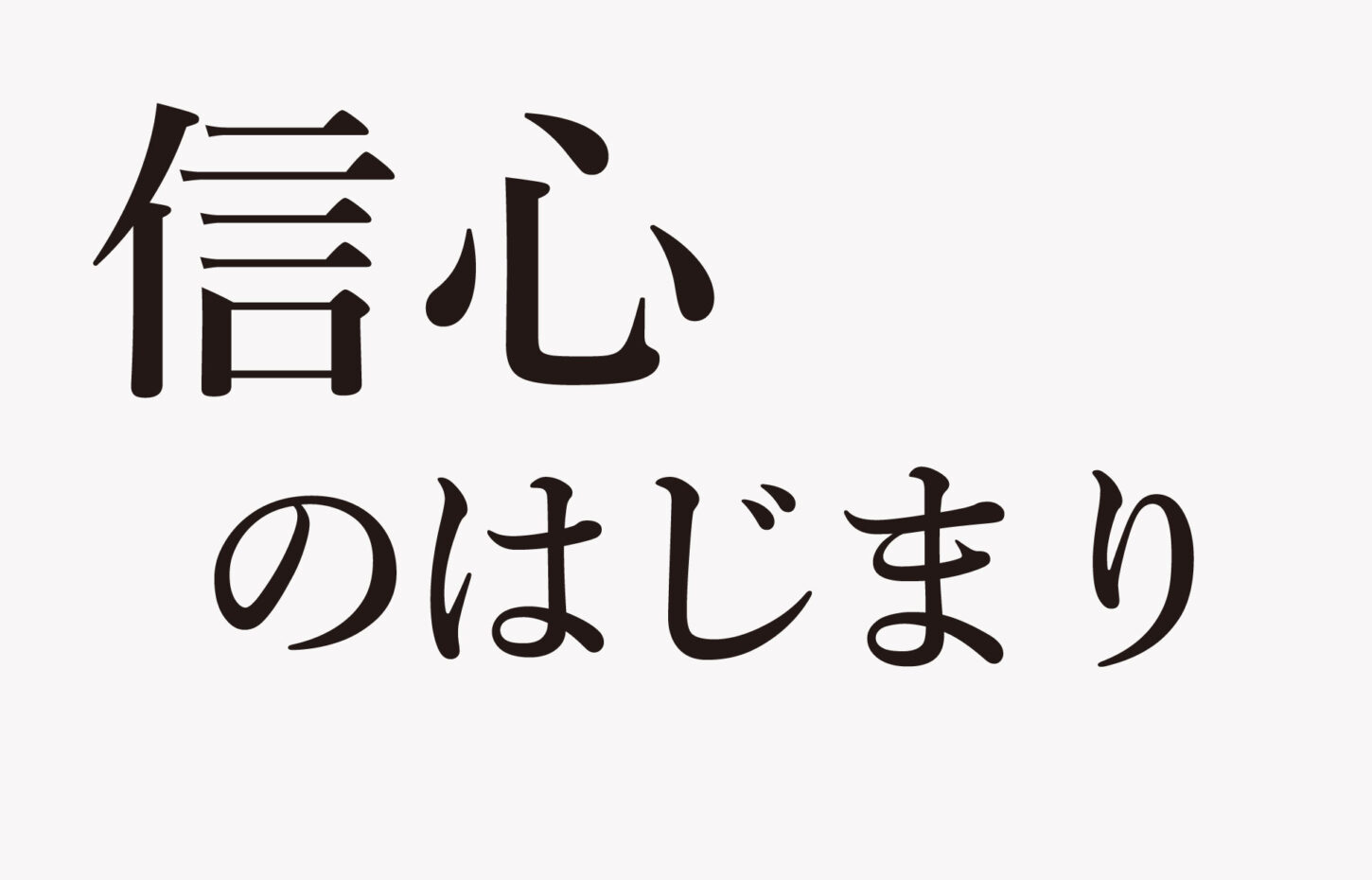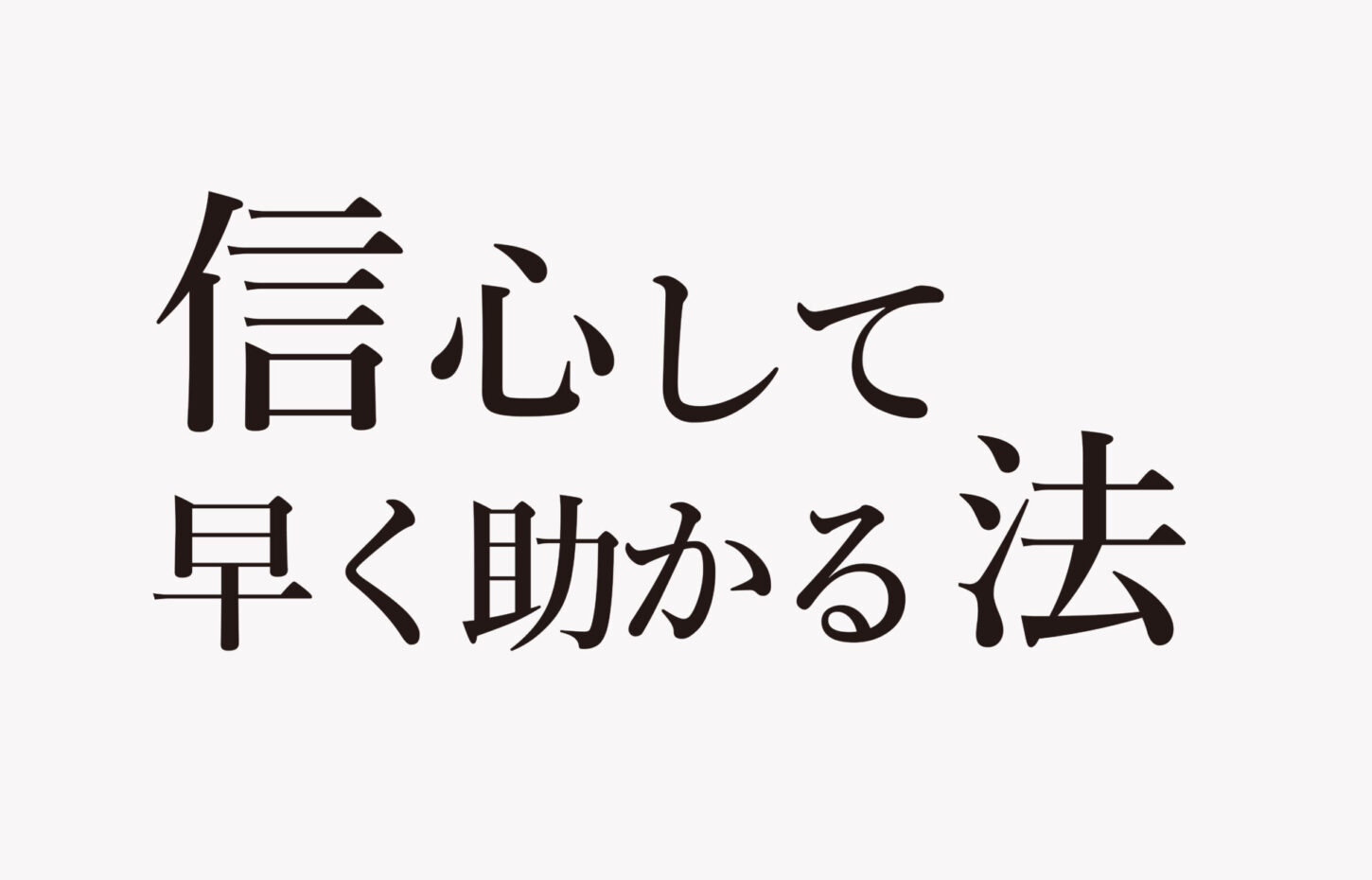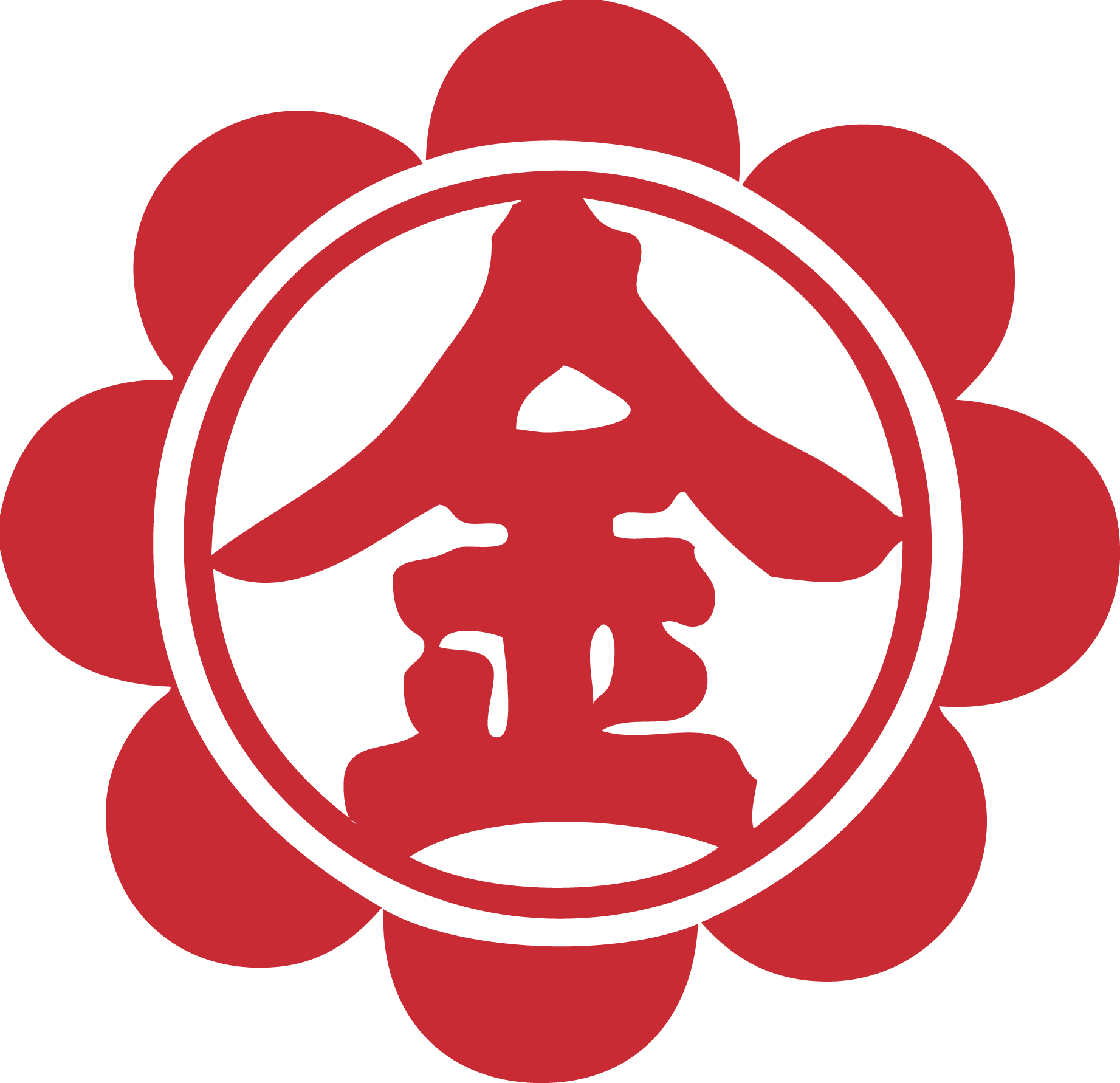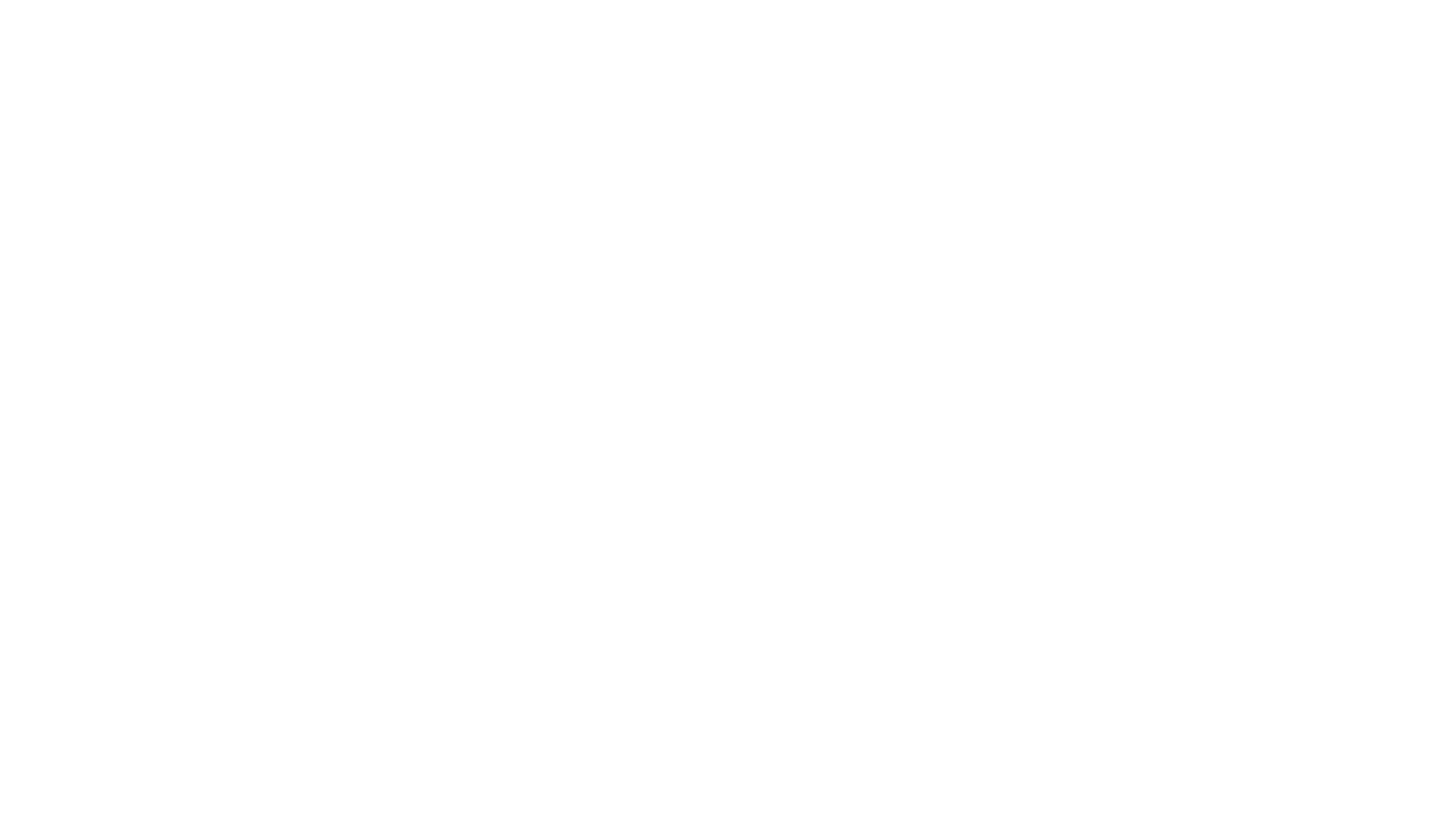難儀に感謝
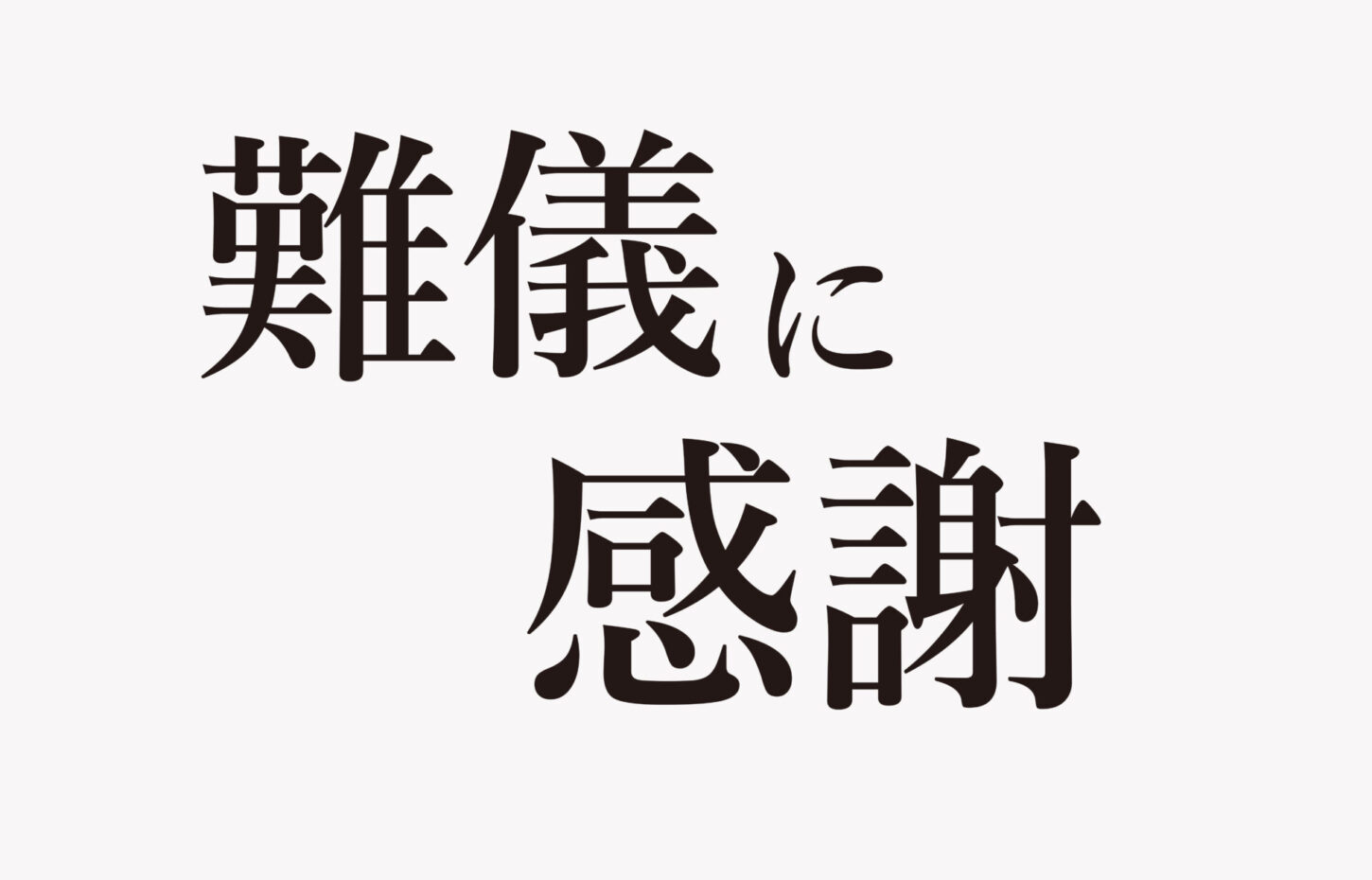
一生懸命信心してきても難儀は起こってきます。信心がまだよくわからないうちは、ちゃんとお参りして手をあわせているのにどうしてこんな問題ができてくるんだ、と言いたくなるものです。
しかし、信心が進んでくると少し変わってきます。難儀は辛い、苦しい。しかし、この難儀があるから神さまに真剣に向かい、自分を見つめなおして進んでいけるのだ。神さまが自分に難儀を向けてくださっているんだ、と漠然とでもわかってきます。
難儀から嫌や嫌やと逃げ回っていくのではなしに、この難儀を通してしっかりご祈念をしていこう。難儀が起こったことが逆に神さまの助けてやろうとのご意志の現れだと、とらせてもらえる。
そしてしっかりと腰をすえて難儀を差し向けられた神さまに感謝しつつ信心を前進させていく。
こういうことができたら信心もたいしたものです。ただ現実にはなかなかこうはいかない。ある
程度信心してお話を聞いていくと、そうあらねばということまではわかる。難儀の重さに引きずら
れたりして、すっとはまっていけない。
そこでお参りです。やはり家で拝んでいるだけでは信心は進みません。とっととっと教会へ足を運ぶ。大先生のお徳の満ちたお広前でご祈念をさせていただく。お結界でお取次をいただく。参拝をすると不思議と前向きになれるものです。
お参りをして信心を練って練って難儀に立ち向かい、おかげに達する。たくさんの信者さんが玉水のお広前で実践してきたのです。
〇年をとっても信心はできる
湯川の家はめぐりが深い。そのめぐりを初代大先生が信心して神さまからお取り払いいただき、徳に代えていただきました。
それでも初代大先生はすべてのめぐりをお取り払いいただこうとは思わない、とおっしゃいました。子孫のために残しておく、と。一見妙なお言葉ですが、先ほどから申してきましたように難儀があってこそ難儀に引っ張られて信心は進むということをふまえてのお言葉であると思います。
そしてこういう信心の営みということは、いくつになってもできるということもありがたい。むしろいろんな失敗を経て、あのときはああしくじったから今度は気を付けようとか、知恵もついてきます。もちろん元気な心でという前提もありますけれども。年をとったからあれもできないし、これも見合わせよう、信心も。ではもったいない。できることはいくらでもあるのです。
信話集に初代大先生が長年信心していたおばあさんの五十日祭を仕えたとき「この家の守り神にとりたてる」とお言葉を神さまからいただいて驚いたという話があります。大先生から見たそのおばあさんはとりたてて素晴らしい信心をしていたようにはみえなかったからでした。で、家族から詳しく話を聞いてみると、その方は家庭円満にことさら気をつかい、トラブルになりそうなことは「私が間違った、私のせい」と自分が引き受けて収めてきたということがわかりました。年をとると自分を大きく言いたいものなのに、小さくなって働くことはできないことと、初代大先生も神さまのお言葉に得心したとあります。
働くことができなくなってもこうして信心はできます。祈ることはできます。
私は三代大先生がお隠れになる直前、痛いはずの横になった姿勢でじいっと『天地書附』を凝視
されていたという話をよく思い起こします。三代大先生の世代の先生は『天地書附』のいただき方
をしっかり教えこまれた世代なので、最後の日に強いご祈念をされて逝かれたのは間違いないこと
です。体が動かなくても信心はできるのです。
(玉水教会 会誌 あゆみ 2025年10月号 に掲載)