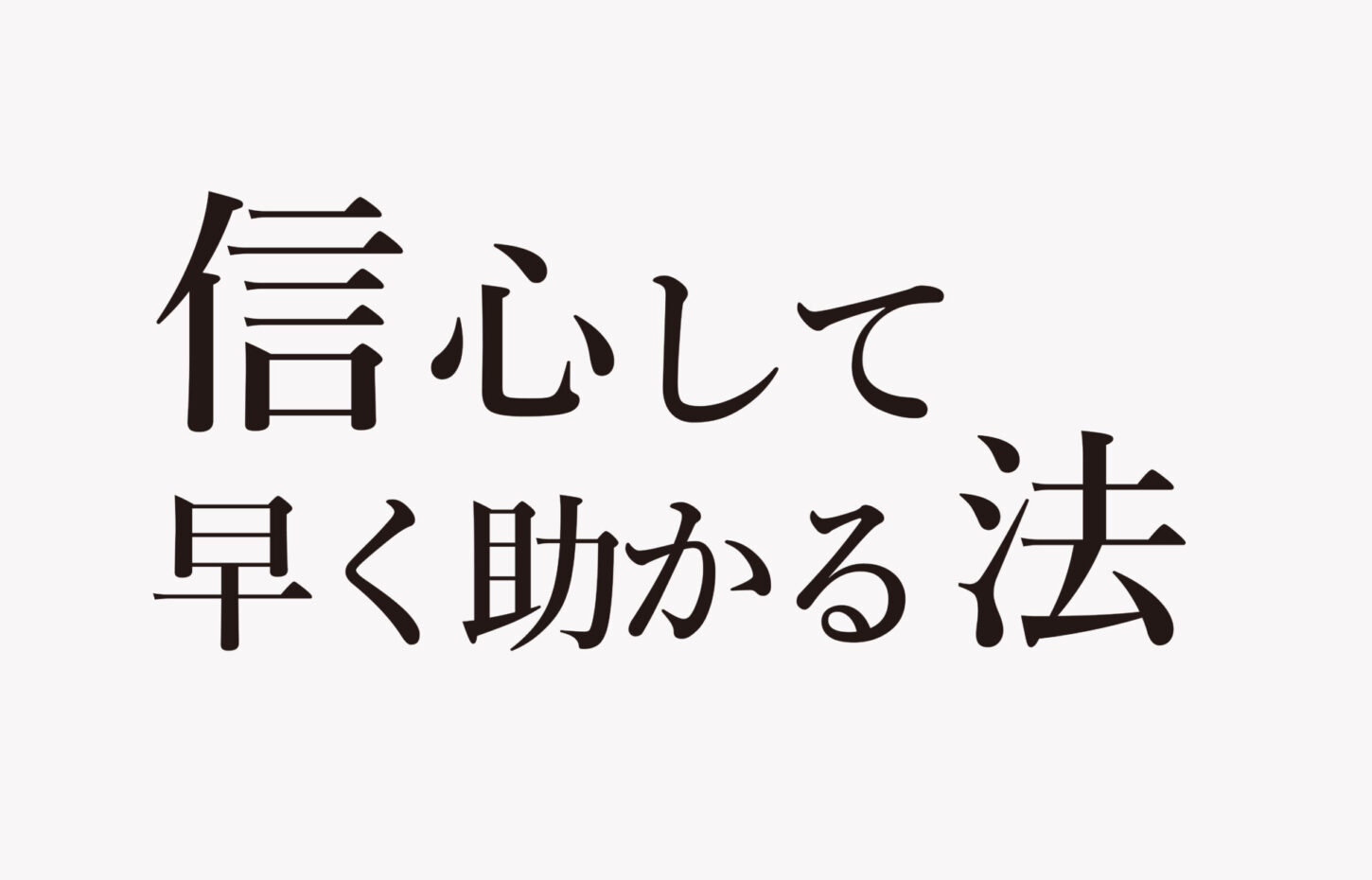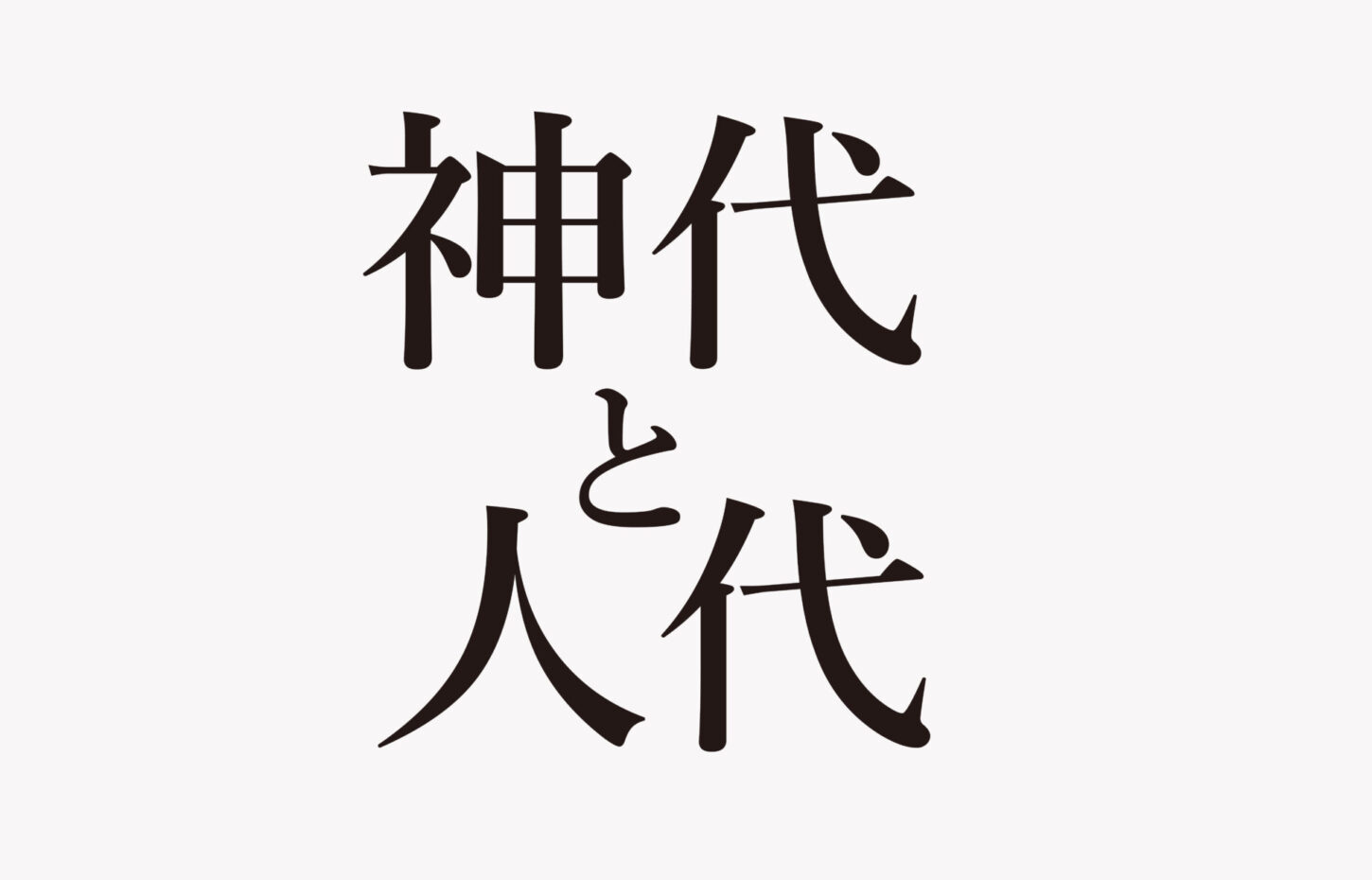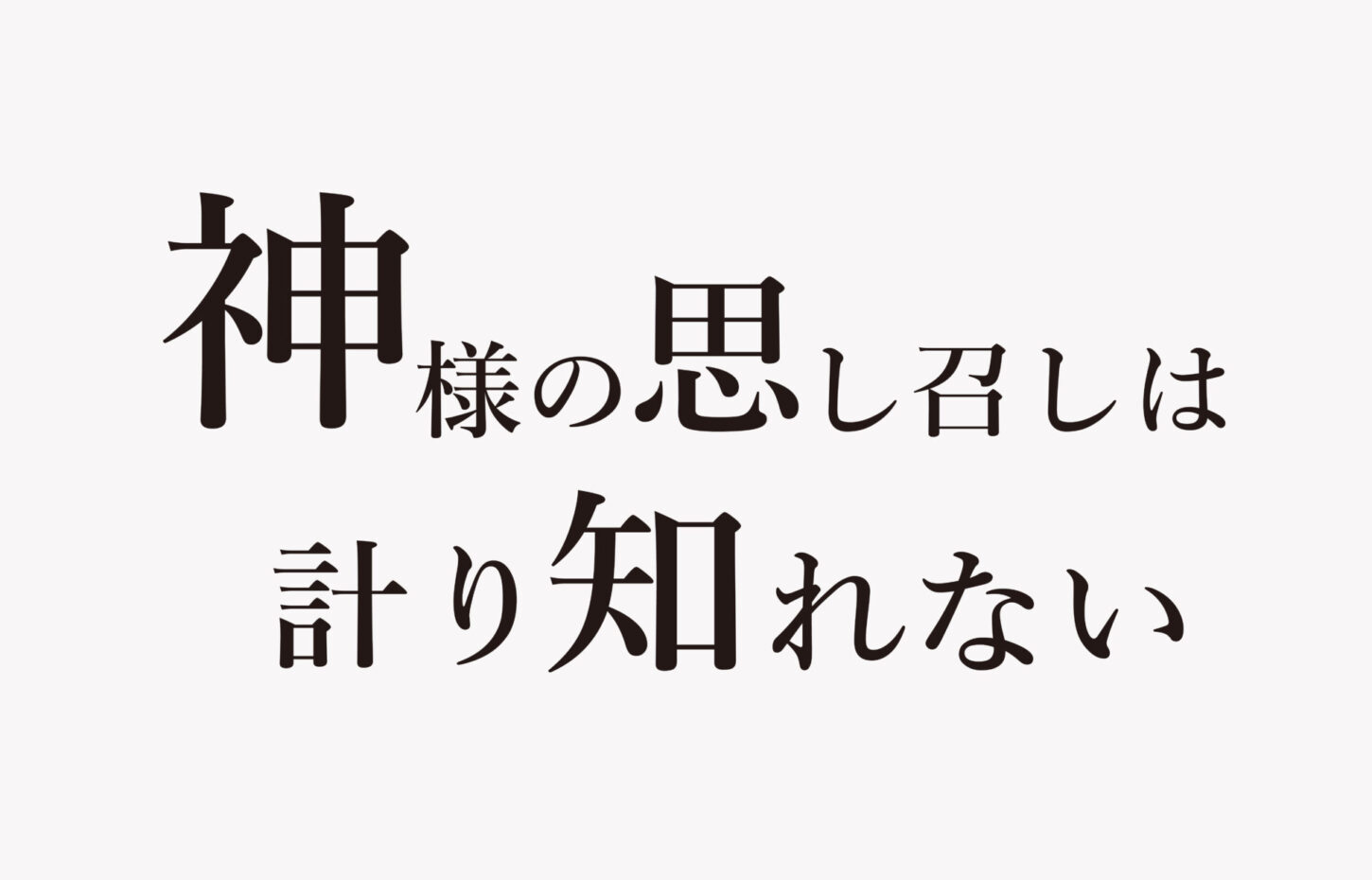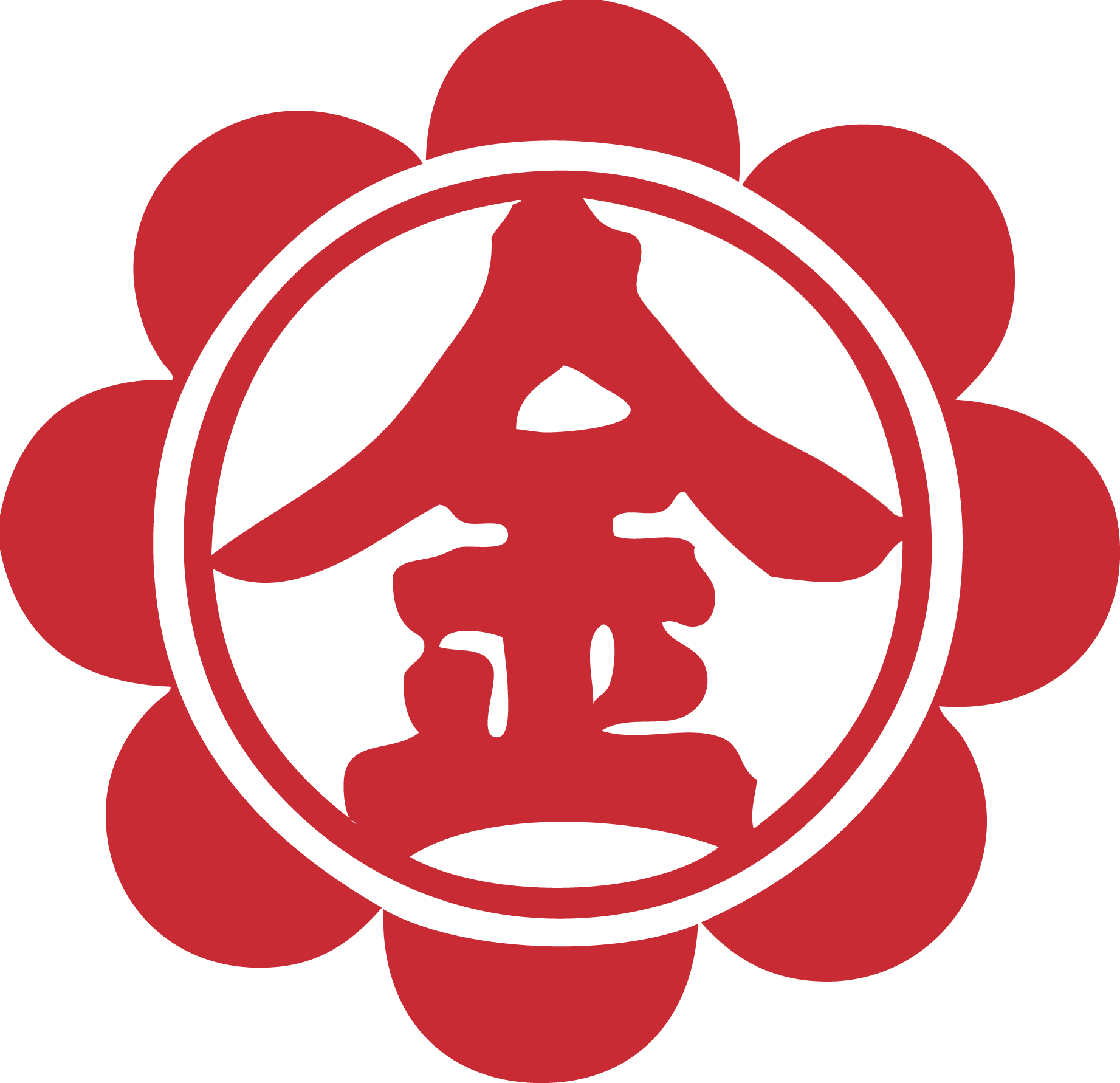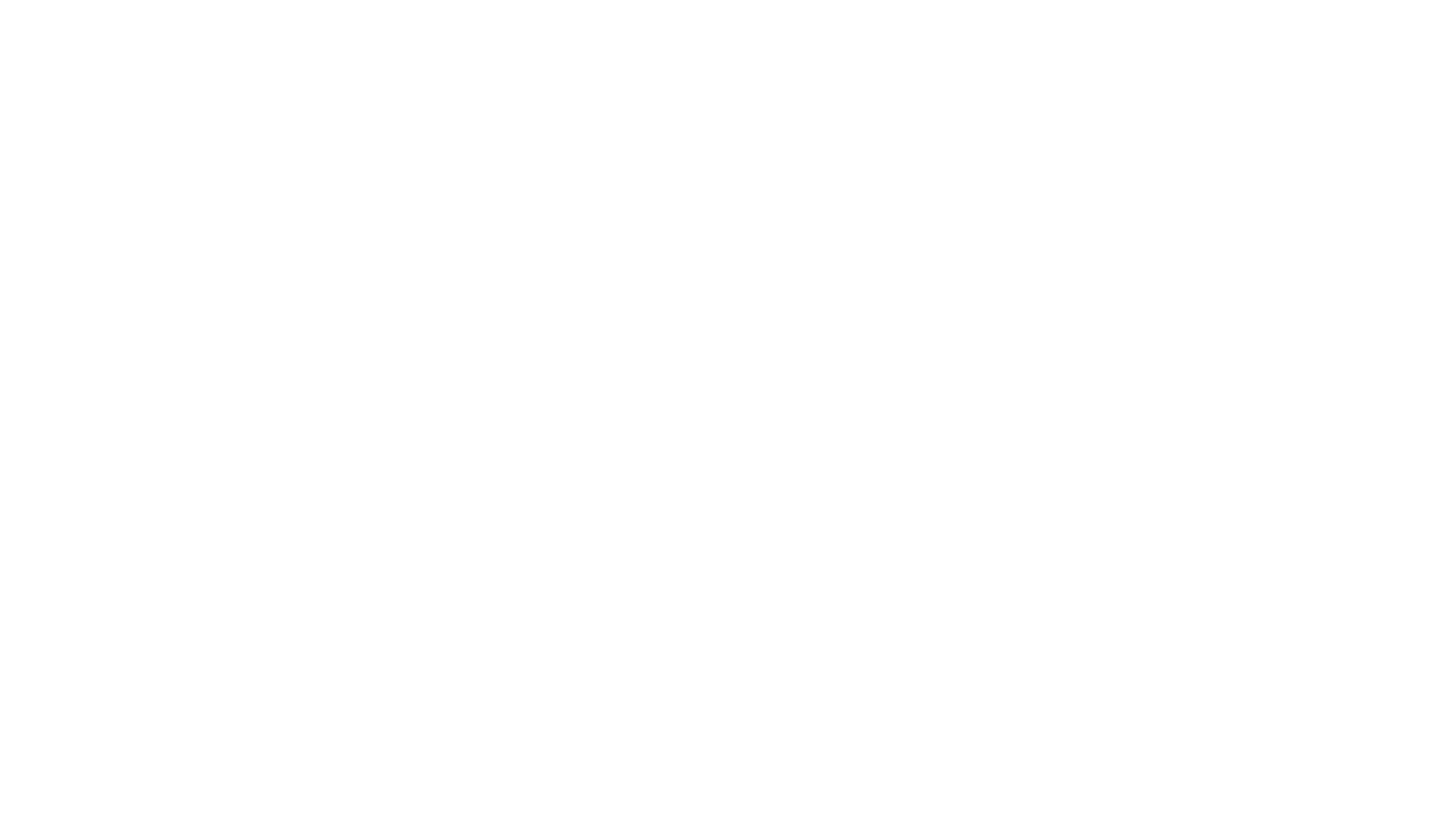信心のはじまり
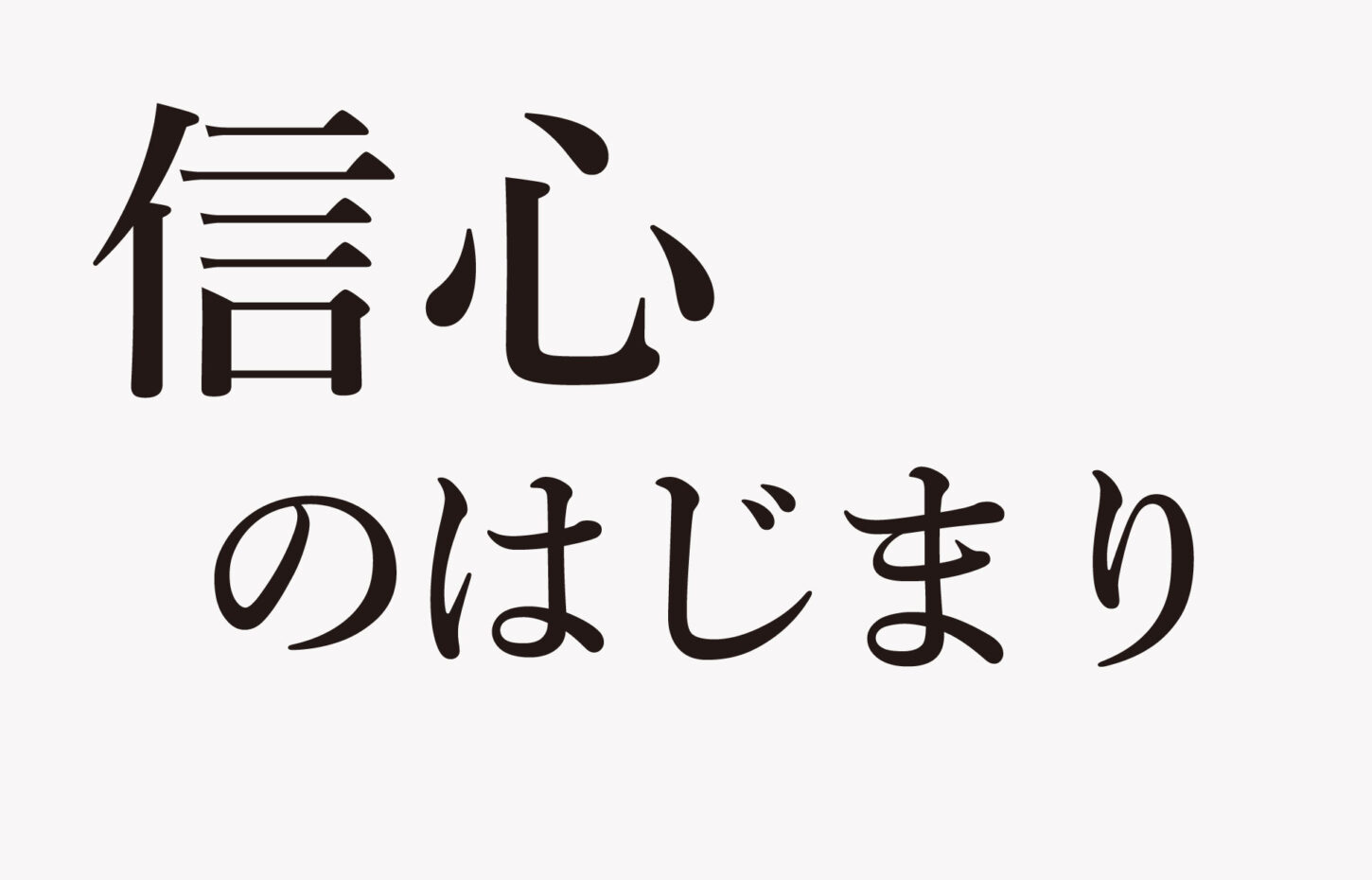
四月二十日にお仕えした、布教百二十年の天地金乃神大祭は素晴らしいお祭りとなりました。何年かに一度の日曜にあたったことでお参りしやすく、最後にスカウトの子どもたちによる「よさこいソーラン」の踊りもあって大いに盛り上がり、お参りのみなさんが大変喜んで帰路に立たれたようでありがたいことでした。
この日の大祭は、玉水教会の始まりを祝うお祭りでした。しかしもっといえば、初代大先生の信心の始まりをいただくということが大切ではないか、と私は考えます。
初代大先生が二十歳で大病したとき、「大恩ある親をおいて死ねません」と神さまに祈って起死回生のおかげを蒙ったのがすべての始まりではないか。だからこそ、玉水の信心において恩ということはとても重い、大きいことではないのかと、そんなふうに私は思います。
〇私の場合は二代大先生
私自身の自覚的な信心の始まりは何か、と振り返ると、それは二代大先生に行き当たります。アメリカで大学生活を送ることができたのは、祖父と父のおかげだったということぐらいは、当時の私でもよくわかっておりました。
一年目の帰国の際、二代大先生にご挨拶に参ると「ああ正夫か」と、とても喜んでくれました。ところが二年目には何かお分かりになっていない様子で、私はショックでした。が、何時間か後に「正夫帰ってきたんか」と分かってくださいました。その翌年には声をかけても返ってくることはありませんでした。
二代大先生はご承知のとおり、初代大先生のお祭り、大祭や霊祭にはお広前に出て玉串を奉奠されていました。アメリカから四年目に帰ってきたとき、何か御用をさせてもらおうという気持ちになって、羽織袴に着替えて、車いすを押して二代大先生をお広前までお連れする御用をさせていただきました。お広前からは彌壽善先生が押していかれました。お隠れになる前年の秋の大祭では体調が悪く、息も荒くて「様子をみよう」ということでした。それが祭典がはじまると、呼吸が楽になってくる、血色も改まってくるという感じで「これはお出ましいただける」と変わりました。お広前で彌壽善先生に導かれて進んでいくお姿は、しかし空(くう)を見ているという様子でした。私は下手から二代大先生をずっと凝視しておりました。玉串も扇子も持てない二代大先生がいよいよご神前に進まれ、向かい合ったとき、二代大先生の目から光がパーッと広がるように見えました。ご神前からも光がさして来て混じりあっている光景が、私には見えました。
その瞬間、私は「もう二代大先生が生きている間に金光教教師にならしてもらわないかん」と思わせられたのです。
あれはいったい何だったのかと、私はずっと考えていました。で結局あれは、二代大先生が神さまと一つになる姿なんだと、感じるようになりました。初代大先生が、信心が進んでいくと新人になり、次いでまことのこころの真心となり、かみごころの神心となって、最後にかみひとと書く神人になると説かれた、その神人のお姿であったんだと解釈しております。
私の信心の始まりが二代大先生の最後のお姿から始まったということは、本当にありがたいことです。親大切から始まった初代大先生のご信心と、親をいただくということでつながっておりますから…。
今年は布教百二十年のお年柄です。どうぞこの一年、自分の信心の自覚的な起点を振り返り、あのおかげをいただいた、親の思いに触れた等々、信心はじめの感動や喜びを思い起して、お年柄にふさわしく信心を展開して、さらに大きなおかげをいただいてまいりましょう。
(玉水教会 会誌 あゆみ 2025年6月号 に掲載)